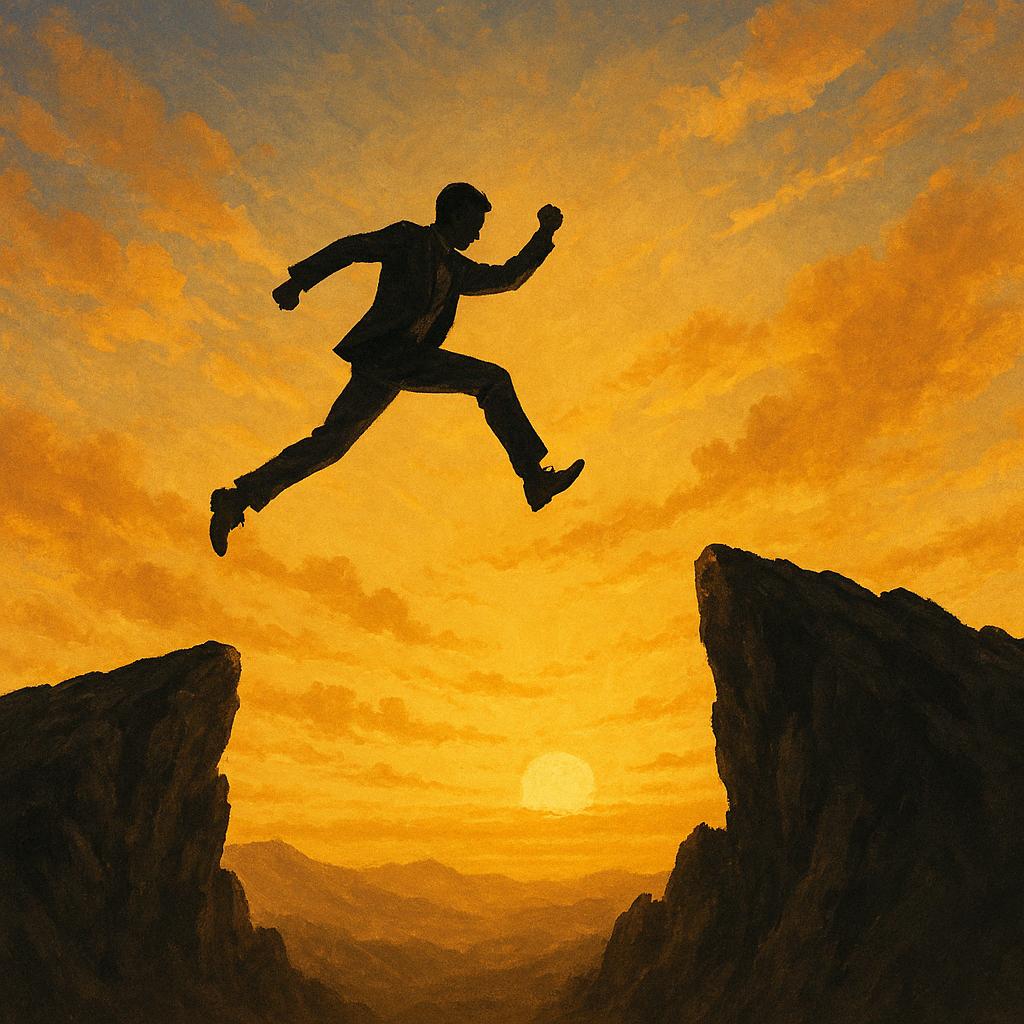
チャレンジしてゴールに到達するためには、優先度が高いものにフォーカスして、自ら持つリソースを集中する必要があります。
というか、そんなやり方をするなら大抵うまくいくものです。
諦めなければね。
でもそれは同時に、相対的に優先度が低いものを不要なものとして手放すということでもあるわけです。
そこには手放す恐怖があります。
一般的に言われていることや、周囲の声などの雑音もあるかもしれません。
特に「普通は…」という価値観から離れるのは勇気が要ります。
だって普通じゃなくなるわけで、その先に進むと何の保証も無く、全ては自分次第。
もっとも、「普通」だったら何か保証があるのかというと、実はそっちも無いのですけどね。
マジョリティーとなることで安心はしていられるかもしれませんね。
この道を選択すると、多くが得られるものを得て、多くが恐れるものを恐れて…
別に悪いことではありませんが、まぁ普通なのです。
さて、どうしましょうか?
と考えたとき、実はすでに答えはあるのではないですか?
普通を選ぶことによって心がザワザワしそうなら、恐らくその選択は自分に合っていません。
時が経った後に後悔するかもしれません。
自分で選んだことなら結果がどうあれ、やらなかった後悔よりはマシです。
それに、チャレンジしたときに得る経験は、きっといつか役に立ちます。これは絶対。
とはいえ、いきなり大きな勇気を振るって、突然凄いチャレンジをする必要もありません。
しても良いですけどね。
まぁ、それも良い経験になります。
最初は小さなチャレンジでも良いのです。
できれば、大きなゴールを定めておいて、その達成に必要なものを未来から逆算してブレークダウンしていきましょう。
そして、今できそうなところまで小さくなったら、それをやりましょう。すぐやりましょう!
そう、最初は小さな勇気でもいいのです。
それを継続するとどうなるか?
最初に小さな勇気でやったこと
これを継続すると自分にとっての「普通」になります。
習慣化しますから。
そうしたら、次の小さな勇気を振るってみましょうか。
そしてそれも継続すると習慣化して「普通」になります。
そんなことを大学在学中継続すると…
凄いことになります。
シンプルですね。
でもきっと、勇気が無くてもうまくいく方法が…
あると良いのですが、残念ながら思い付きません。


