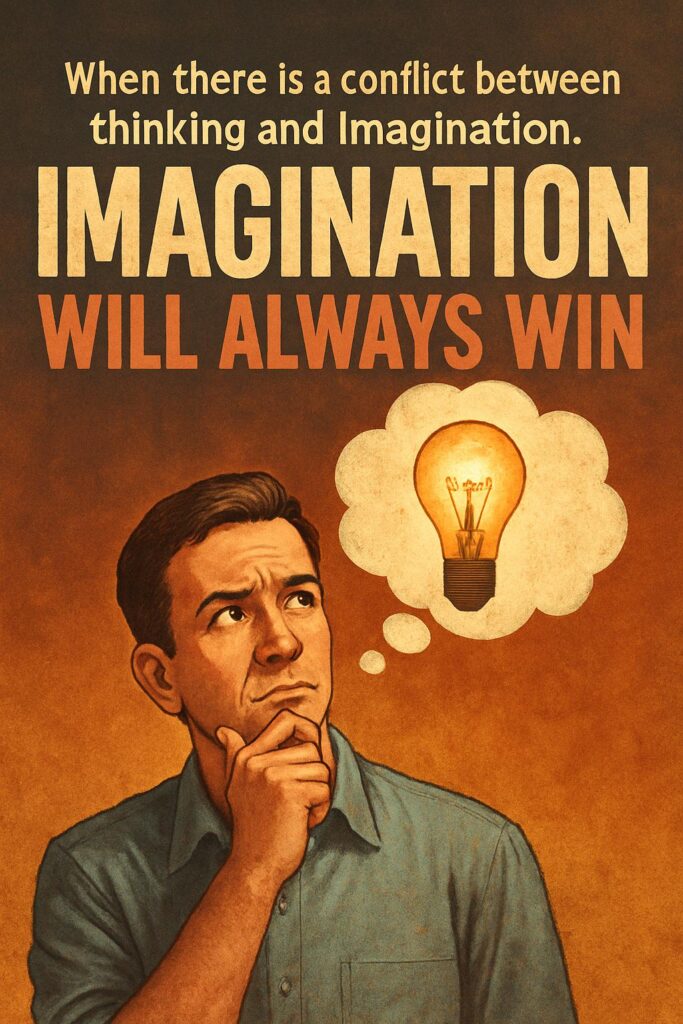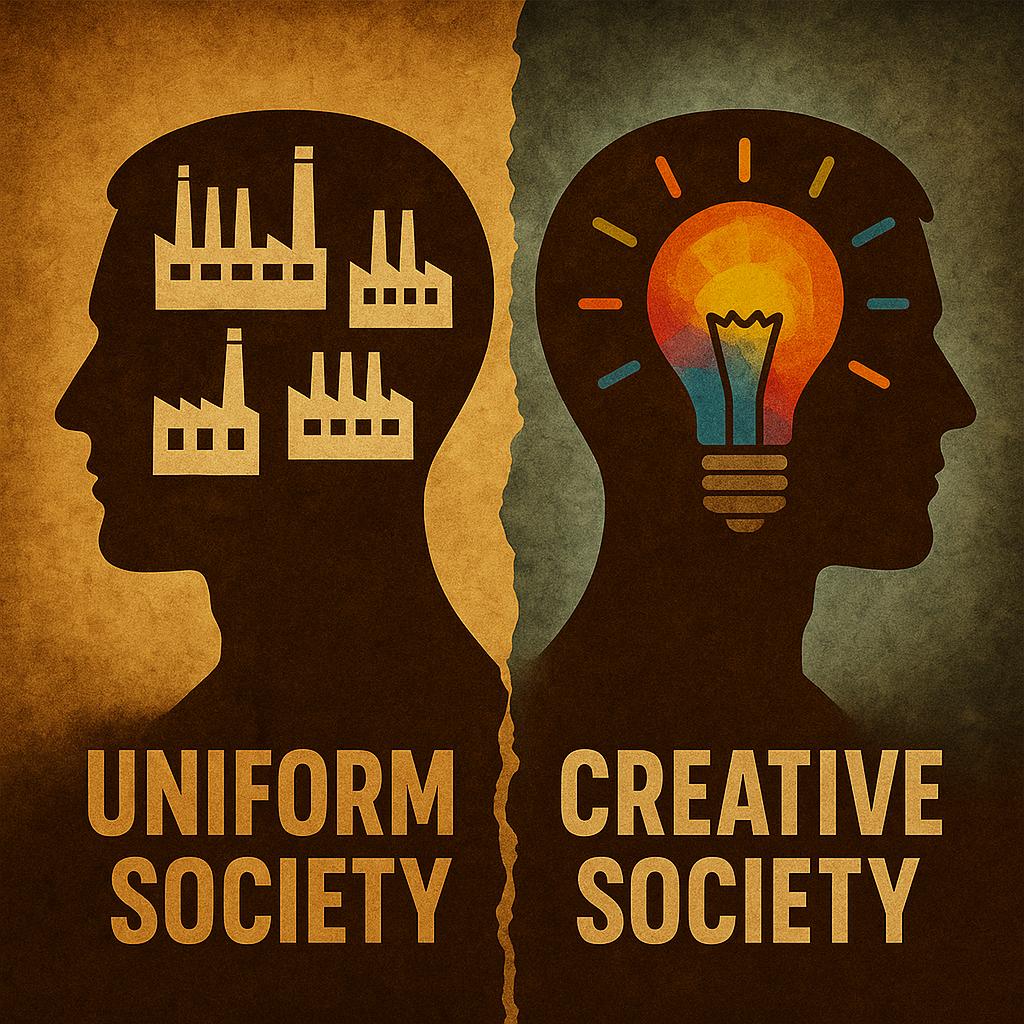
かつて我が国には「一億総中流」と呼ばれる時代がありました。
これ、貧富の差が少なく、多くが特別豊かではないが、貧困でもない、という状態だったのです。
それが長いこと当たり前だったわけですが、世界的に見たらとても珍しい状態だったのですね。
そういう状態を支えていたのは、大きく二つの原因があると思っています。
一つは、高度経済成長のベースとなっていた、大量生産体制。
向上で安価で高品質な製品を大量に生産していた。
そしてもう一つは、そのための一定の知識やスキルを持った人材が大量に必要になるわけで、そういったニーズを満たすための教育システムの確立。
そんな状態が長いこと続いてきたのだけど、このやり方は人件費が安くて人口が多いのであれば成立するけど、それらのいずれか一方が維持できなければ継続は難しくなる。
で、人件費が上昇し、人口が減少した現在に至る。
もちろん低コストで大量生産のビジネスモデルはとうに成立しなくなっているのだけど、教育システムの基本形は変化せず。
言われた頃をやるという機械的な能力の重視と、考えることよりも記憶力をベースとした教育という形は変わっていません。
このシステムのトレードオフとして、尖ったヤツが少なくなるということなのですが、だからこそ貧富の差がない、均質的な社会が実現する。
興味深いのは、一億総中流であった頃よりも、むしろ今の方が人は均質化しているような気もすること。
まぁ、教育システムが同じ形で続いているならそうなるのは当然か。
問題は、この先どうしていくべきなのか。
社会の形は変わろうとしている。(すでに変わっている)
教育は未来の社会のためにあるのに、旧来の形のまま。
その形を保てば、かつての一億総中流に戻れるわけでもない。
なので、このままで良いはずは無い。
とはいえ、均質化から脱却して、個性や自発性を重視した自律的な教育に変えていくとどうなるか?
やはり二極化するのかな。
するのかもなぁ。
でも、それ以外の方法があるのだろうか?
その辺を考えるのは恐ろしくも難しくもあるのだけど、きっと避けては通れない道。
何か良い方法があるはずだ。
とか考えていると、やはり新しい時代がやってくるのは必然なのだろうな、と思うのです。
どうせなら、面白くしていかねばなりませんね。