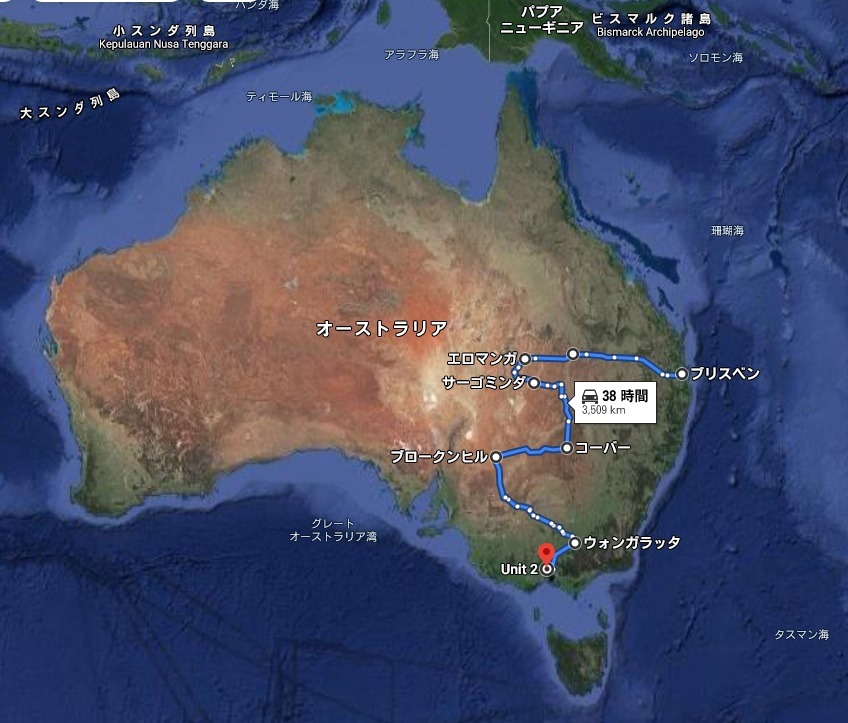頑張って努力して成長して
それがずっと上り調子で続いていけば良いのでしょうけど
決してそんなことは無いですね。
上がったり下がったり
調子が良いときもあれば悪いときもある。
良いときは何をやってもうまく行く気がしたり
悪いときは何をやってもうまくいきそうもなかったり。
植物が季節の移り変わりに伴って
種子から芽が出て花が咲いて実がなって葉が落ちて
そんなサイクルを繰り返しながら成長して
いつかは終わりを迎えるように
人にも成長のサイクルがあって
芽が出て花が咲いて実がなって葉が落ちて
それに該当するようなことを繰り返しながら成長して
いずれは終わる。
人によって多少の違いはあれども
たぶんそのサイクルは絶対的なものでしょう。
「葉」が落ちたというのに
「実」を求めても無理なように
今の立ち位置に不相応なものを求めても
そりゃぁうまくいきません。
そう考えると
バイオリズムなんてのは
かなり当たり前なんですね。
ちなみにバイオリズムは
20世紀初頭にオーストリアの生物学者によって提唱されたもの
とChatGPTが言っています。
バイオリズム
生きとし生けるものの持つ周期ですね。
なるほど、納得。
植物だって動物だって
周期に従って生きています。
我々人間だって同じでしょう。
でも、ひょっとして
人はそのサイクルに抗うことによって
文明の発達を手に入れたのかもしれませんね。
今の自分がサイクルのどこにいるのかが分かれば
何をすべきかが分かるわけで
それに適したアクションを取っていれば
とても自然で、そこそこうまくいくでしょう。
でも、個々の力でできることには限りがあるわけです。
それを「社会」という集団の力で
ブレークスルーすることを決めた人間の場合は
周囲の環境(社会)が
個々の持つサイクルに従うことを許さなかったりするわけで。
でも、その環境があるからこそ
一人では為し得ないことができる
というトレードオフが効いています。
だから代償として
今の自分が成長のサイクルのどこにいて
何をすべきかが分からなくなってしまって
悩み苦しむのかもしれません。
そんな気がしています。
こういう考え方
自然信仰との親和性が高い日本人なら理解しやすいと思いますが
どうでしょうか。