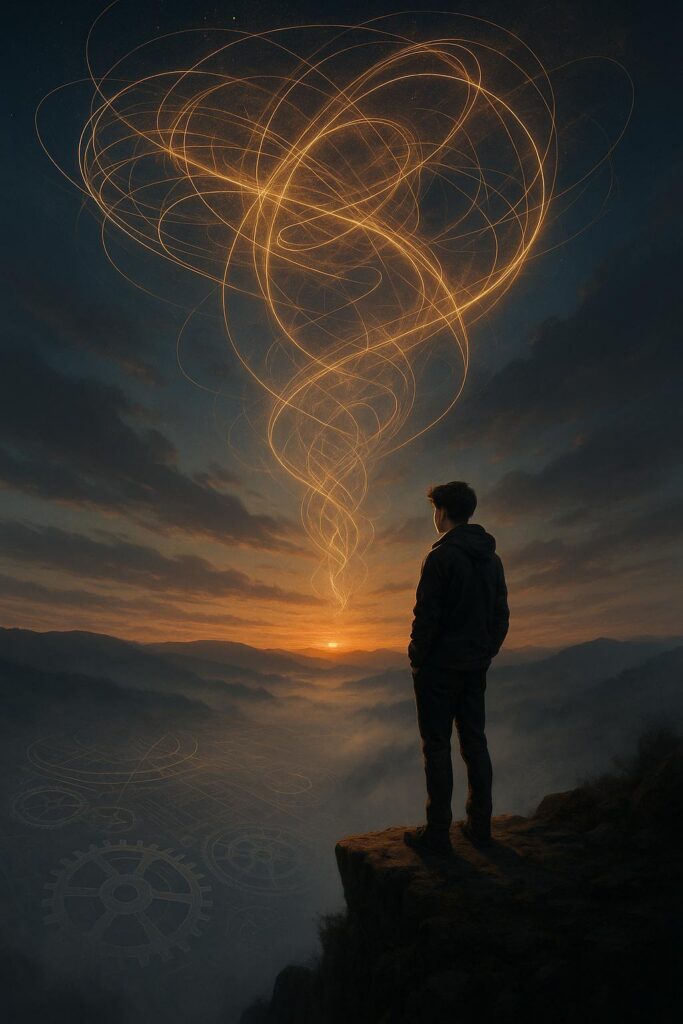成功するためには
熱意とか勇気とか好奇心とか諦めない心とか
そういったもののワンセットが必要となる
とはいうものの…
これ、考えているだけでは良く分かりません。
やってみない限り、何が足りないか分からない。
ただ、経験があまりない場合は、やってみても分からないことも多い。
そんな時は経験者による評価が効いてきます。
そういう意味では学校という存在は大きい。
ただ皮肉なことに、現状の学校はマルかバツかの評価をする場所になっている事がい多いため、その環境に慣らされてきた学生にしてみると
不足しているということは不正解でダメなことだ
と判断する価値観が身に付いてしまうのですね。
確かにペーパーテストでは、そういうことになってしまうのですが、何かをできるようになっていくプロセスでは、不足している状態からどうしていくかが重要。
この現状からどう抜け出すか。
これは問題です。
考えてみれば最近の世の中は、多くのことがマルかバツかで極端に評価されているような気がしなくもない。
ちょっとでもリスクがあれば、それはバツだ!みたいに。
これも学校教育の弊害でしょうか。
「教え」は、教員からの一方通行で
その成果はペーパーテストの正解・不正解で測る
といったことを日々繰り返していたら、そうなるのも仕方ない気がします。
でも、そこから抜け出さないと、チャレンジはできないし、向上心も萎んでしまう。
ともかく
何が不足しているかを知りたい
足りないものが必要だ
と思う気持ちが重要です。
となると、スタート地点である動機が重要ということですね。
これ、知能とかそういうことではなく、心の問題だと思うのですが、どうでしょうか?