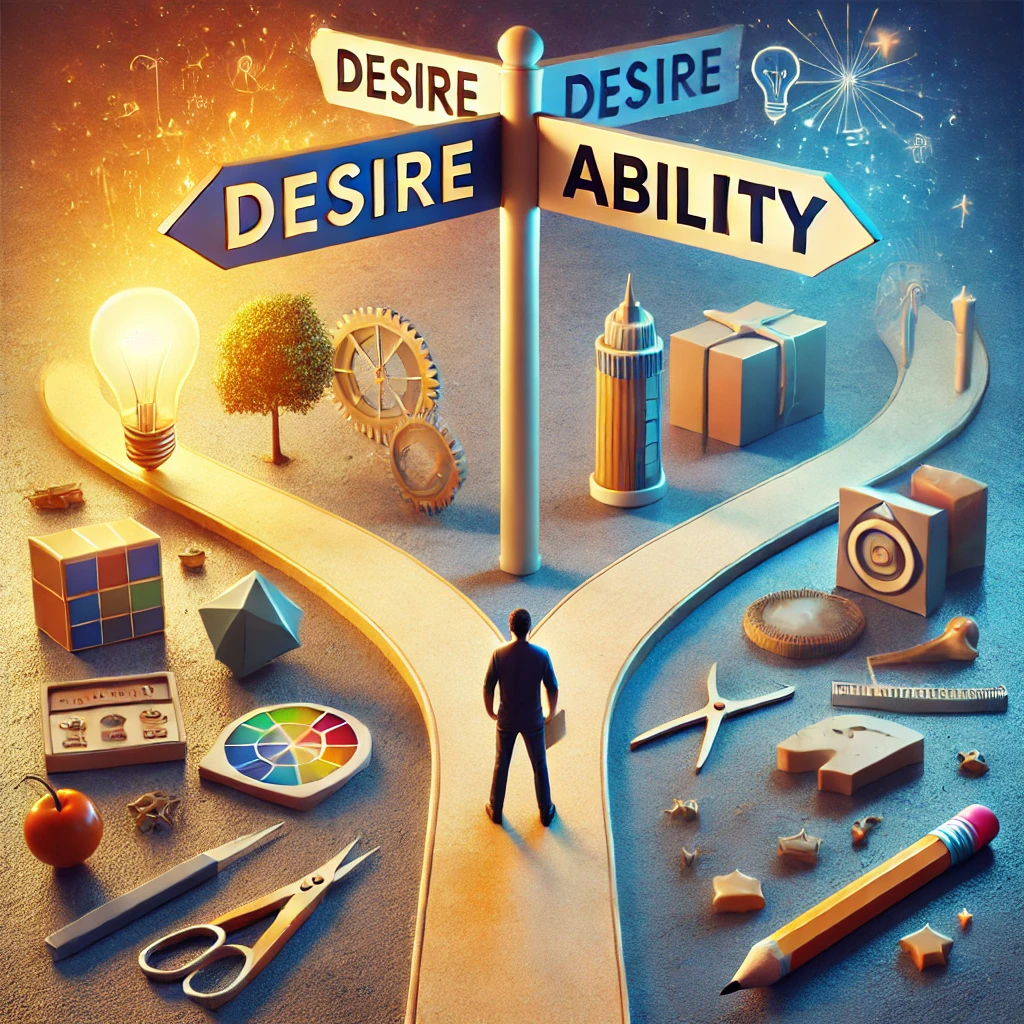「自分はこんなとき、こうする」ってのがあるでしょう?
そういうお話しです。
良い事が起きたら喜ぶ
とか、そういう当たり前のことは大して問題にはなりません。
だって良い事が起きているのですからね。
大事なのは、その逆です。
困難な状況、危機的状況でどうするか?
そういった状況でこそ、自身が問われます。
困ったことに、そういった時に発動するのは生存本能やら防衛本能で、無意識のうちに反射的に行動していたりします。
それが悪いとかいう話ではありません。
善悪じゃなくて
それじゃ面白くないよね
とか
それじゃ価値が無いよね
とかいった話です。
困難は、かつての自分が原因を作っています。
それによる結果が起きて、それに対する反応はいつも通り。
だったら、その後も今まで通りで、同じ事が起きます。
そう、困難な状況こそ、試されているのです。
そこで面白いことができるか?
そこで価値ある行動ができるか?
そこで求められるのは、一般的な当たり前の行動では無いのです。
でも、かといって正解も無い。
まぁ、色々やってみて
「自分ならこうする」
を構築したらいいでしょう。
ヒントになるのは…そうだなぁ…
「逆」をやるといいですね。
皆がやる逆のこと。
これ、冗談ではありません。
面白いことや価値があることって、どういうことで構成されているでしょう?
大抵は、独自性とか希少性でしょう?
ありふれたものには価値は感じられませんものね。
基本的に、皆がやらないこと、やりたがらないことって価値があったりするのです。
だから逆をやる。
困難に遭遇したら、眉間にしわを寄せたり、俯いている場合じゃありません。
その時に、キミにとっての「逆」をやってみましょう。
きっと面白いことになりますよ。