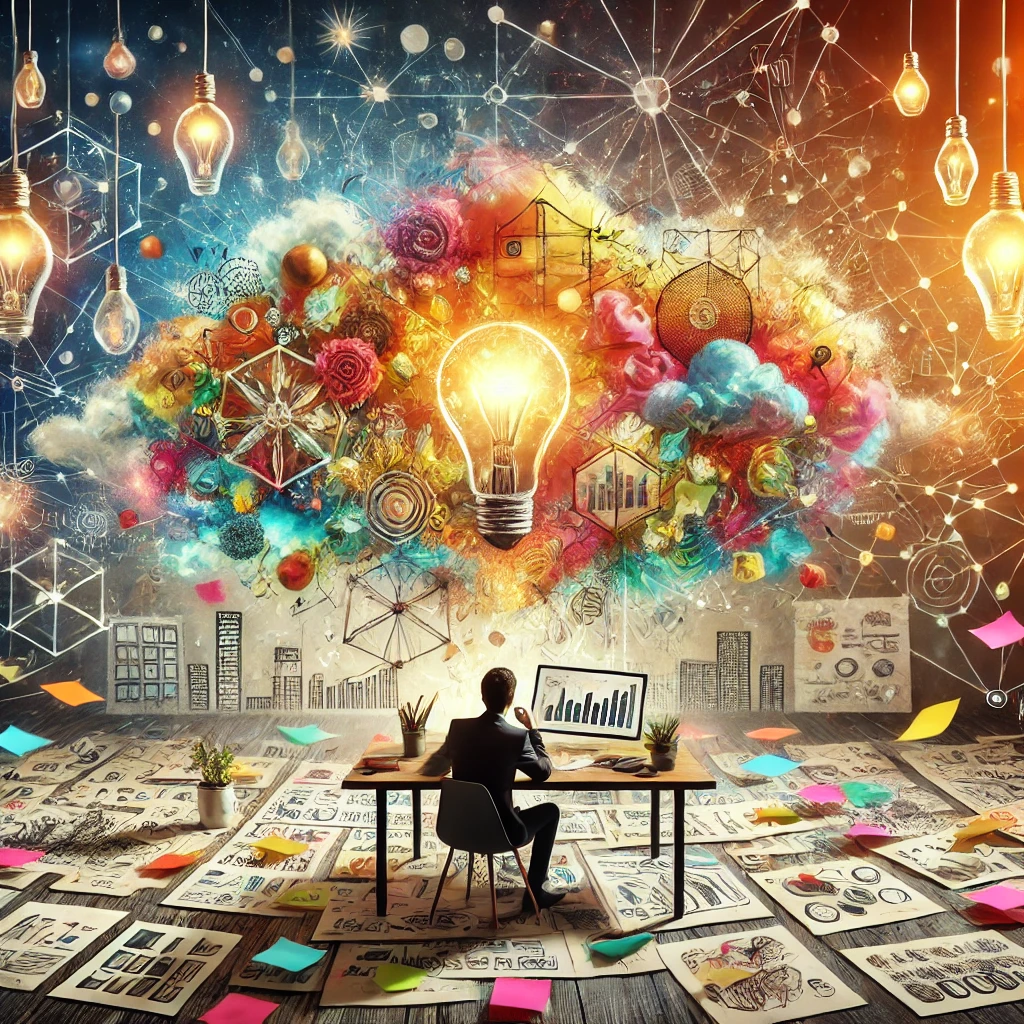誰でも心配をした経験があるでしょう。
今日は、「心配」について考えてみました。
特に、ビギナーのチャレンジャーにおいて、です。
心配しているとき、どういう心理状態になっているのでしょう?
例えば恐れだったり、ネガティブなことが起きる予感だったり
いずれにせよ、未来に関することですね。
過去のことについては心配とは言いません。
で、それらを予想・想像して、心がザワザワしちゃってる状態でしょうか。
そんな時、我々はネガティブなことが起きると信じています。
その可能性が大きいとか小さいとかはあるでしょうけど。
違いますか?
だって、ポジティブなこと、ニュートラルなことであれば、心配なんてしないでしょう。
さて、問題はこの先です。
ネガティブなことを考えていれば、もしくは信じていれば、それは実現します。
「えー?超能力者じゃないんだから…」
と思いますか?
別に不思議はありません。
自分で思ったことを自分でするのだから簡単です。
ただ、自分の頭では、心配の対象は「良くない」ことだから嫌だ、と分かっていても、深層心理はそうはいきません。
ヤツはそういう良いとか悪いとかの判断はできないのです。
これはだいぶ前に記事にしましたね。
それに、単純に考えても、ネガティブなことを思いながらポジティブなことをやるって、おかしいというか難しそうじゃないですか?
まぁ、はっきり言って無理だと思います。
我々の行いは、思いから発していますから、きっと大したことはできません。
はい、ここでタイトル
信じた事は実現する
ネガティブなことが起きると信じていると、ネガティブなことが起きるのです。
納得いきませんか?
そして、心配ばかりしていると病気になります。
心の病だけでなく、体の病気の元ともなるのです。
免疫力が低下したり、我々の体内で日々凄い勢いで行われている細胞分裂に、エラーが生じたりするからだそうです。
これ、遺伝子工学の学者さんが実際に研究されています。
ただ、あながち悪いことばかりではなかったりもします。
心配は、未来への準備や問題解決など、良い仕事に繋がることもありますから。
例えば、「フールプルーフ」とか、「フェイルセーフ」なんていう手法というか、考え方があったりします。
簡単に言うと、しょうもない操作をしても事故が起きないような設計にするようなことです。
興味がある人は調べてみると良いでしょう。
ともあれ、何事も多面性があるってことですね。
さて、ではポジティブなことを信じていれば、ポジティブなことが起きるのか?
そりゃ起きるに決まってるでしょう。
ネガティブは信じるけど、ポジティブは信じない?
まぁ、よくある話ですけどね。
人は誰しも成功より失敗の経験の方が多いので、ネガティブな経験の方がリアリティがあって、そういうことになりがちです。
それに、ポジティブなことを信じていれば、仮に想定外のことが起きても、その経験はきっといつか役に立つと思えたりするでしょう。
それだけでも心のノイズが無くなって、良い仕事ができそうじゃないですか?