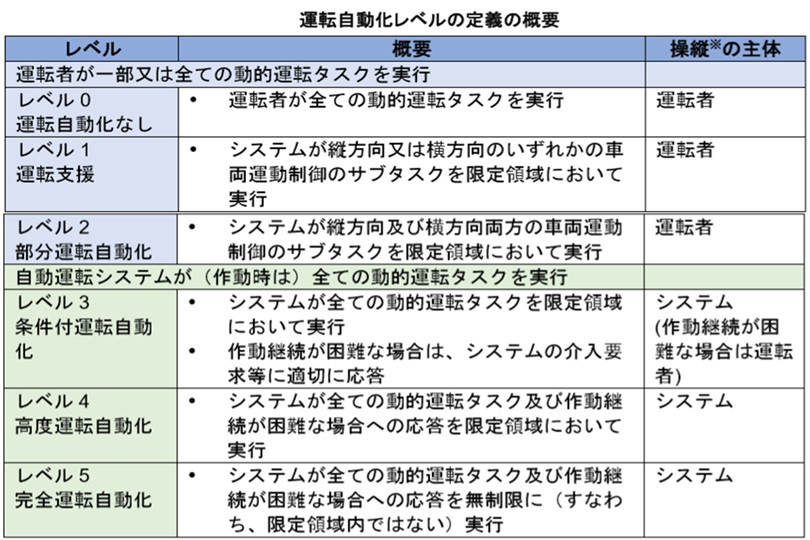ハイラックスを車検に出したので代車を借りました。
以前は整備やら車検やらは可能な限り自分でやったものですが、最近は時間や労力の都合もあってすっかりお任せです。
で、信頼できる地元の整備屋さんにお任せしています。
その整備屋さんは、スズキのディーラーでもあるので、当然ながら代車はスズキの場合が多くて、毎回「最近のスズキは良くできてるなぁ」と関心するのです。
質感や居住性はもちろん向上していますが、動力性能や操縦安定性もかなり良くなっています。小型車も軽も。
今回の記事はたまたまマツダを出しましたが、スズキもマツダも味付けこそ違うものの、最近のクルマは総じて良くなっている気がします。
10年くらい前から格段に良くなったような気がします。
で、何が良くなっているか?
感心しちゃうのは、何と言ってもハンドリングです。
まず直進時、中立付近の直進性が良い。
路面の荒れによってフラフラせず、しっかり落ち着いた感じ。
操舵時は、狙ったとおりに頭が入るので、分かりやすい。
旋回時の姿勢もしっかり感があって落ち着いています。
もちろん設計的に良くなっているのは想像が付くのですが、この分かりやすく信頼できる感じは一体どうやって得ているのか。
こういう設計って、むやみに反応を良くすればいいってもんじゃなくて、適度な遅れと反応の大きさがあるのです。
遅れが小さくて反応が良すぎると、ドライバーには過敏で乗りにくい印象を与えますし、もちろんその逆でも乗りにくさを感じます。
その辺の最適化は、設計である程度はやりますが、社内にいる操縦安定性評価のエキスパート(テストドライバーの親分みたいな人)が自ら試作車を運転して官能評価によって行います。
で、この時点でのチューニング(味付け)が最終的なフィーリングを決めるのです。
もちろん、設計的にダメなものはいくらいじってもダメなので、良い設計であることは前提ですが。
それらは正解とされる値があるわけでなく、数字に表しにくいことです。
なので、設計者が良い値がを出せば済むものではありません。
この最終的な評価を担当するテストドライバーは、操縦技術や車体に関する豊富な知識はもちろんですが、凄いセンシング能力も持ち合わせています。
どのくらい凄いかというと、テスト車両に装着したセンサーが読み取れないことも彼らはセンシングしたりします。
品質とか性能とか、目に見えるとことはもちろん重要なのですが、クルマは走るものなので、走ったときにどう感じるの?というのが最重要で価値の根源だったりするのですね。
本当に大事なものは目に見えないのですよ。