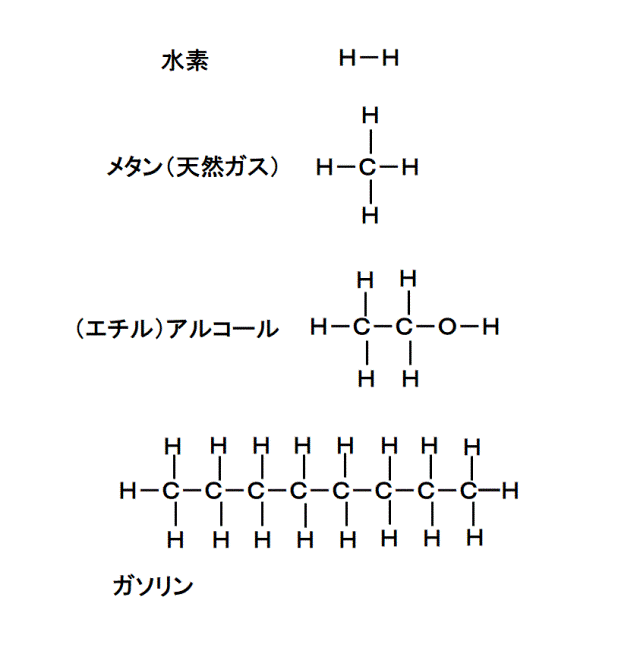どんなクルマにするか考える
狙ったとおりになるように考えて設計する
狙ったとおりになるように作る
狙った性能が出るように実走行でセッティングする
こんなプロセスで学生達はレーシングカーを作っていますが
完成したクルマはもちろん
それぞれのプロセスにおいても
何が起きるか分かりません。
だって十分な経験がないのだから
それは当然です。
解析や強度計算がうまくできると
部品単品としては思った通りになるかもしれません。
しかし
それらを組み合わせて
実際に使う(走る)と何が起きるか分からない。
それは
作っている人間の
想像の領域の外のこと
イレギュラーなことが起きるからです。
いくら勉強しても
いくら慎重に設計しても
そういうことは起きます。
現実の世界では
イレギュラーなことは
常に起きる可能性がある。
要因は無数にあります。
授業ではそういうことは起こりません。
時間内に予定されたことを
学べるように考えられているからです。
たとえば
実験の授業では
どんな結果が得られるかは
最初に決まっています。
イレギュラーな結果が出てしまったら
授業が終わらないからです。
本来は
何が起きるか分からないから
「実験」するのであって
最初に何が起きるか分かっていることを
やるのは本来の「実験」ではありません。
でも、授業では「実験」と称して
本当の実験をやるときに
必要なことを学ぶのです。
決して無駄ではありません。
さて
設計の際に
狙ったとおりのことが起きるようなマシンにするために
よーく勉強して
すっごく慎重に設計して
あらゆるイレギュラーな事象を想像して
設計すると何が起きるか。
間に合わなくなります。
レースに。
勝つためのクルマを作っているはずなのに
そもそもレースに間に合わなくなります。
特に学生の活動の場合
時間的にカツカツですから。
なので
今の自分たちには
どんなやり方が効果的なのかを考えて
チームの方針を定める必要があって
その重要性を全メンバーに落とし込む必要があります。
こういうのは授業では学べません。
最近はあまり聞かなくなりましたが
Formula SAEの重要なことの一つに
Real Deadline
があります。
直訳すると
「本当の締め切り」
です。
レースには色々な締め切りがあります。
大会へのエントリー
自分たちの開発スケジュール
レースのスタート時刻
などなど
これらの「本当の締め切り」を守っていかないと
自分たちのミッションは果たせません。
なので
最も効果的なやり方で
開発を進める必要があるのです。
設計段階で
色々考えすぎて時間を使ってしまうと
実走行による最適化のための時間を失っていきます。
いくらよーく考えてマシンを作ったところで
完成したときに得られる性能は
当初の想定よりずっと低いはずです。
大抵はガッカリします。
そして
そこから性能を上げていくのです。
それこそが学びです。
そうやって学んだことは
決して忘れません。
プロでもそんなもんです。
なので「試作車」が必要なのです。
走らせてみないと
実際にやってみないと
分からないからです。
チャレンジしている学生達には
やると
分かる
その面白さを味わって欲しいものです。
色々経験していくと
「やらなくても分かる」領域が拡大していきます。
そうなると
やることのレベルをどんどん上げていけます。
そのループに乗せられれば
ますます面白くなってくるでしょうね。
分かっていることを積み上げていけば安心だし
そういうやり方が必要な世界もあるでしょう。
別にどちらが偉くて
どちらが劣っている
なんてことはないですが
もしチャレンジできる環境にいるのであれば
とにかく色々やってみて
起きる事象に対応する度に試されて
その度に学んで成長していく
そんな毎日も良いのではないでしょうか。
学生生活なんて
迷ってるうちに終わっちゃいますよ。