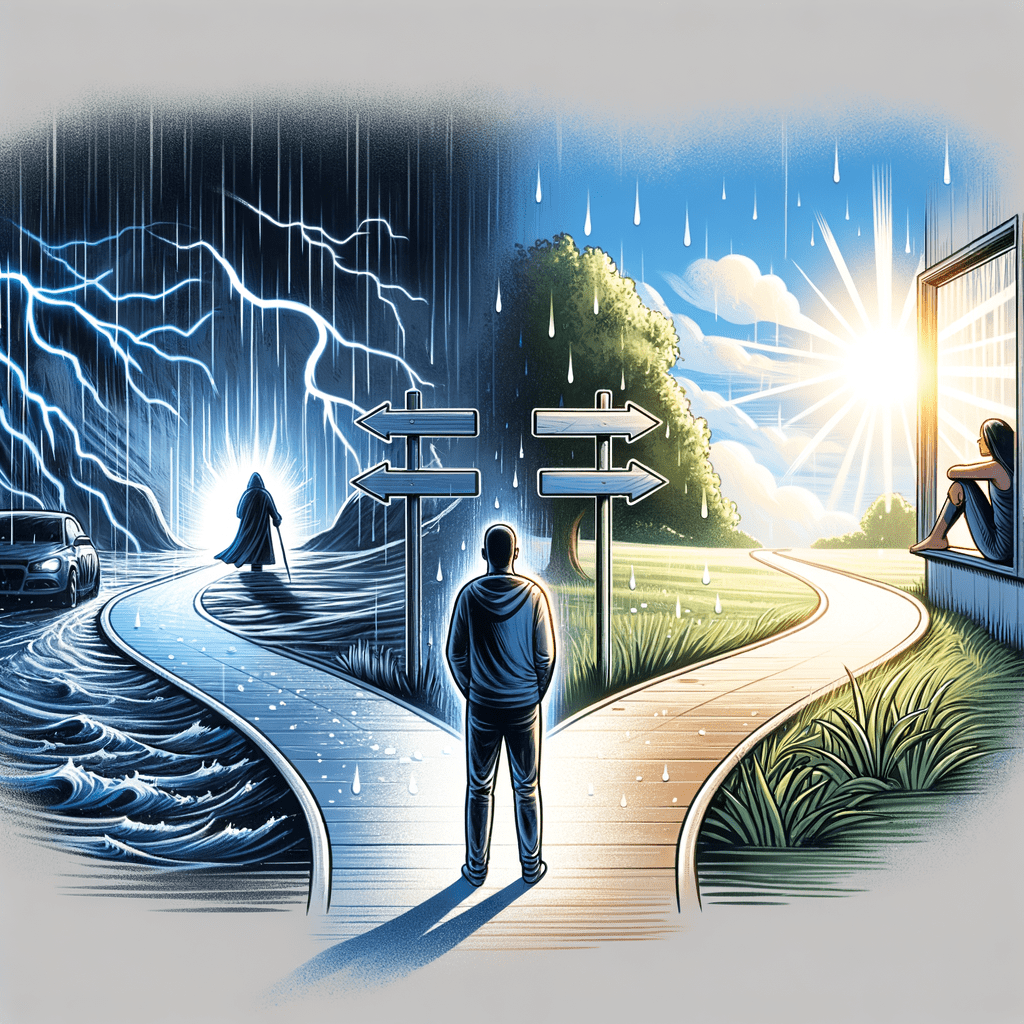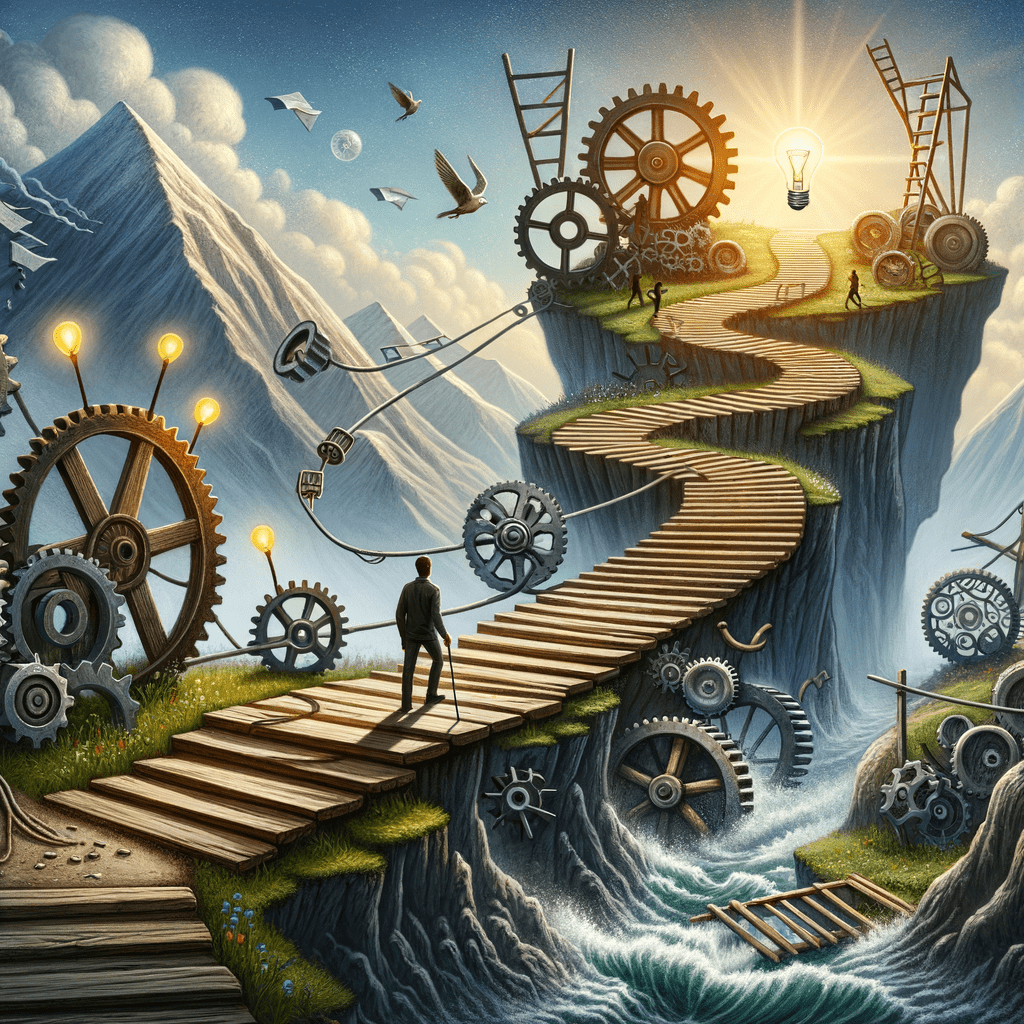ゼロヒャク思考見たいな二元論で考えていると、メンタル疾患になりやすいのだそうです。
それはそうだろう。
世の中の事なんて、大抵はきっちりゼロとかヒャクとかなっていないから。
なので、そのどちらかにしたいなんて希望は叶いません。
学校の教育は、「正解」か「不正解」かで評価します。「できた」か「できない」かです。。
なので当然「正解」を求めるわけで、100点は「完璧」です。
こんなことが生活の中心になれば、当然ながらその他のこともこの価値観に引っ張られるでしょう。
ものごとは「正解」か「不正解」かだ!みたいに。
もちろんそれは、無意識下で。
正解を追求するのは立派なことかもしれませんが、世の中に完璧なものなんて無いと言い切っても良いほど存在しません。
成長においても同様で、ゼロの状態から一気にヒャクにはなりません。
ちょっとずつの変化を繰り返して、徐々に成長していきます。
ゼロヒャク思考でいくと、毎日徐々に成長していても、「まだ完璧じゃない」が繰り返されます。
やってもやってもまだ完璧にはなれない。
そして、その不十分なところにフォーカスし続けていると、「できない感」が習慣として定着してしまう。
それによって「どうせ…」となってしまうこともあります。
ところが、やる気があって頑張る者の心にも影響が及んでいることがあります。
何かをやるときに、ゼロの状態からいきなりヒャクを目指すなんてのがありがちな話です。
当然、そんな方法は思い付かないので考えるわけですが、考えたって無理なものは無理なわけで、どこまでも考えて考えて…時間切れとなりがち。
それによって「やる」経験をすることができずに、知識も経験も得られない。
当然自信も身に付かないので、次のゴール設定は「最低限」を狙うようになったりします。
それを何とかするために、あまり高いところを狙わずに、基本的なことをコツコツと…?
惜しい!
ゴールは高い方が良いのです。
じゃないと、そもそもモチベーションが上がらない。
問題は、その高いゴールに達成するために、まずやることは何か?というところまでのブレークダウンができないことです。
そのために必要なのは、想像力とか経験とか、やはりチャレンジする勇気だったりします。
よく「小さな成功体験を」とか言いますが、いつまでも小さい事ばかりやりなさいということではありません。
デッカイゴールのために、小さい成功からスタートして、継続しましょうよ、ってことです。
やめなければ失敗ではありません。
続けられるようにする工夫も大事ですね。