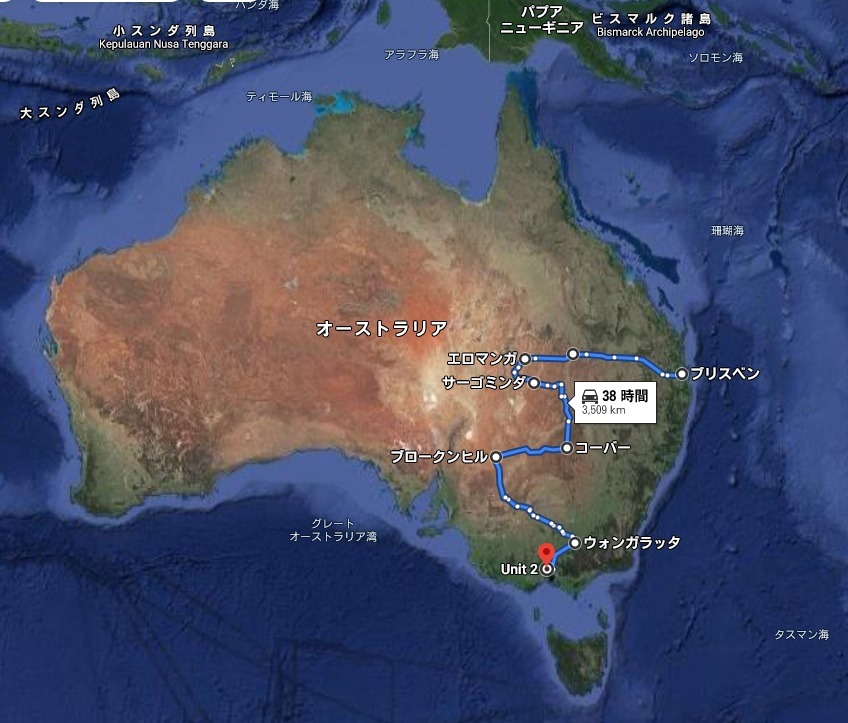フェリーは北海道付近では結構揺れました。
船酔いする人にはキツかったかも。
小樽フェリーターミナルで下船して、早朝4時30分に出発。稚内に向かいます。距離は360km。
稚内から利尻に渡るフェリーは10時10分発なので、1時間前の到着が理想です。果たして間に合うか?
まぁ、仮に乗り遅れても、その次の便があるのですけど。
札幌を通過して留萌までは高速が通ってます。
早い時間なのでガラガラです。
留萌を過ぎて小平(おびら)の道の駅でトイレ休憩と給油ポイントの確認。
フェリーに乗る前に満タンにしましたが、果たして無給油で稚内まで行けるかが問題。
この時6時30分。
周辺のガソリンスタンドは8時営業開始の所ばかり。
ずっと高速だと間違いなく給油が必要だけど、留萌以降は一般道なので燃費が良いはず。
このまま行けるところまで行ってみましょう。

海は荒れてます

特産品とかが入ってます
小平からは日本海沿いに北上。景色の良いオロロンルートで稚内へ。
このコースはとても日本とは思えない雄大な景色でお気に入り。…なのですが、燃料の残りが気になって仕方ない。
結局、稚内にはガソリン残量1Lで到着。ギリギリでした。
ちょっと早めに着いたので、北端到達コインを入手。これで4極全てが揃いました。


稚内からはハートランドフェリーで利尻島へ。
風が強くて歩くのも大変。もちろんフェリーは揺れる揺れる。

かなり激しい揺れの中、1時間40分後に利尻上陸。ちょっとゲンナリしました。
昼食をとったら島を一周してみましょう。
利尻島は1周50km程度なので、ただ走るだけなら、1時間ちょっとで回れちゃうと思います。
フラフラ立ち寄りながら回ってみましょう。
まずは利尻島郷土資料館

昔の町役場の建物を使った資料館。小さいながらも島の歴史と自然に関する紹介が充実してます。
興味深かったのはヒグマの話です。
北海道と言わず、日本最強の動物といえばヒグマなわけで、それはもう洒落にならない恐ろしさなわけですが、そもそも利尻島にはヒグマはいなかったのだそうな。
でも、たまにヤツらは海を渡って北海道からやってくるのだそうです。最短でも15kmくらい離れてるのに。かつて2回(だったかな?)確認されてるようです。
1回は、海を泳いでいるところを発見して、「こいつに上陸されたらエライことになる」ってんで、斧でやっつけた。これが100年くらい前の話し。
で、次は平成です。
この時は直接姿を見た者はいないけど、足跡や糞で上陸していることを確認したそうです。で、無人カメラを仕掛けてみたら、やはりヒグマだった。
島民の皆さんは戦々恐々で、山に入るのをやめたり罠を準備したり。それはもう一大事だったそうなのですが、どうもその後、ヤツは島から出て行ったそうです。姿を見せないまま、痕跡も無くなったと。
で、これにて一件落着かと思いきや、昨年(2022年)の7月に目撃情報があったそうです。今は一体どうなっているのでしょう?
必要以上にヒグマで盛り上がってしまいましたが、沼浦展望台です。
ここからは立派な利尻富士(正式名称は利尻山)を拝めます。
島の真ん中にこんなに立派な山があるのだから、それはもう島のどこからでも見えるといえば見えるのですが、こんなに雄大なアングルで見ることができるのはここだけかもしれません。

このシーン、北海道銘菓「白い恋人」のパッケージに採用されてるんだそうです。なのでここは「白い恋人の丘」と呼ばれてます。
とはいえ、曇っていて寒くて、風が強かったので、バイクから降りることすらなく現地を後にしました。
この後は、利尻町立博物館に行って、その後は早めに宿に行って温泉かな?と思っていたら、雨が降ってきたので、早々に撤収決定。
海と空はこんな感じ。

ホテルに向かう道すがら、おや?と思って立ち寄ったのは…

麗峰湧水と呼ばれる美味しい水。
これ、本当に美味しくてビックリでした。
結局、島の4分の3を回ったところでリタイヤ。
泊まるのは町営のホテル利尻。外観の写真はありませんが。
ここは温泉が良いです。食事も良い。
町民の皆さんで頑張ってる感があって素晴らしい宿です。


周囲は海に囲まれていて、利尻富士も見える…雲に隠れてるけど。
さて、これで今回のミッションは完了です。
明日の朝一の便で利尻を出ます。