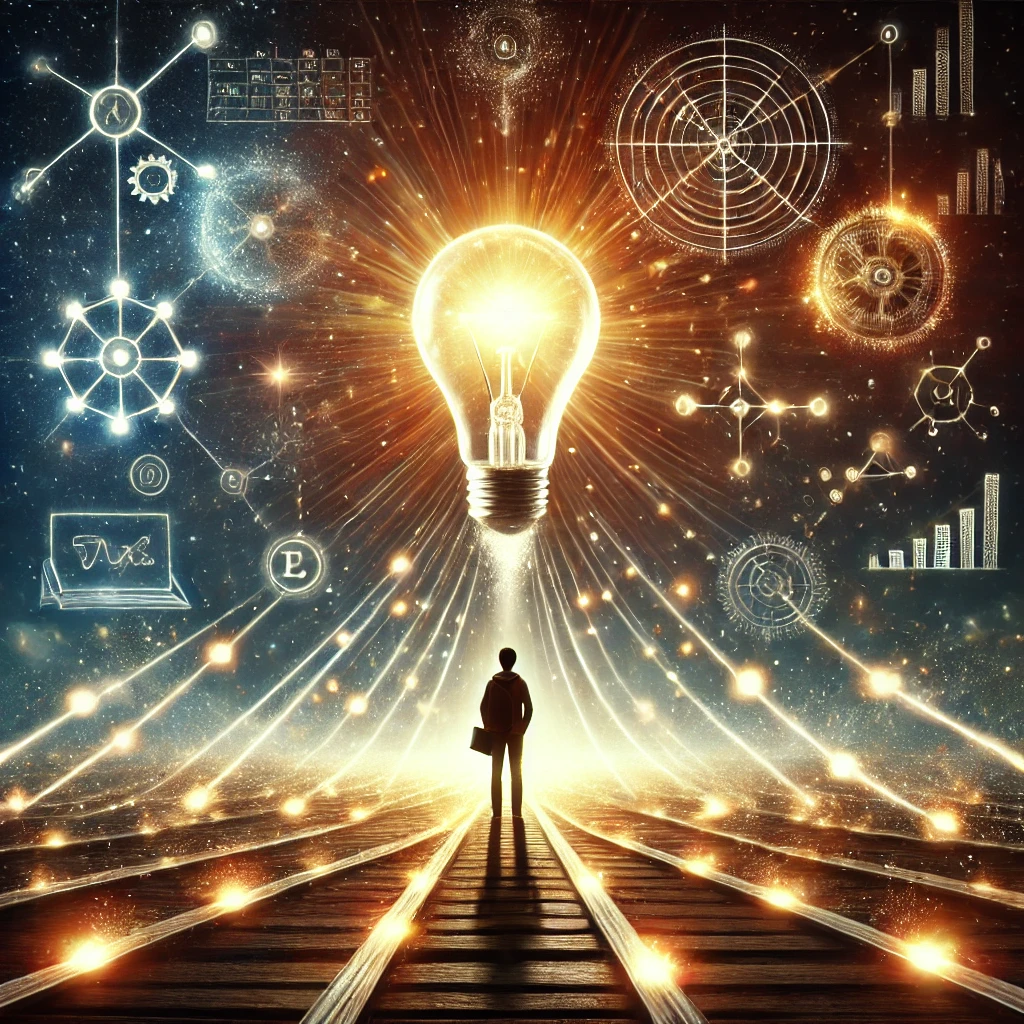
アイデアを形にするために必要なのが知識やスキル。
とはいうものの、基本的な知識ってのは大事です。
国語とか算数、理科、社会なんてのはそういうものです。
で、その辺を一通り手に入れたあたりで、ボチボチ行きたい方向へ来ましょうか、ってことで、実用的な知識とかスキルを手に入れ始まるわけで。
その「行きたい方向」の先にあるのが、ゴールですね。
そこで夢を実現するために必要なのがアイデア。
そして、アイデアを形にするために必要なのが、知識とかスキルってわけです。
そう、ここが重要で、知識とかスキルはアイデアを形にするために「必要」なのです。
必要だと思うからこそ、それらを吸収できるわけで、その順番が逆では形にならない。
アイデアが出る状態、必要性を感じることが重要。
知識さえあればアイデアが出るのかというと、大抵はそんなことはありません。
目的も無しに得た知識をどう使うか?
それによって何ができるか?
そんな風に悩む人が多い気がするけど
本当は順番が逆で
欲するもののためにどのような知識が必要か?
どうやってそれらを手に入れるか?
そんな風に考えて工夫することが大事なのですね。
で、まずはやってみる。
やればやるほど、やらないと分からないことが得られる
何が足りないか分かる。
そんなものです。
やってみもせんで何が分かる
まさにその通り。


