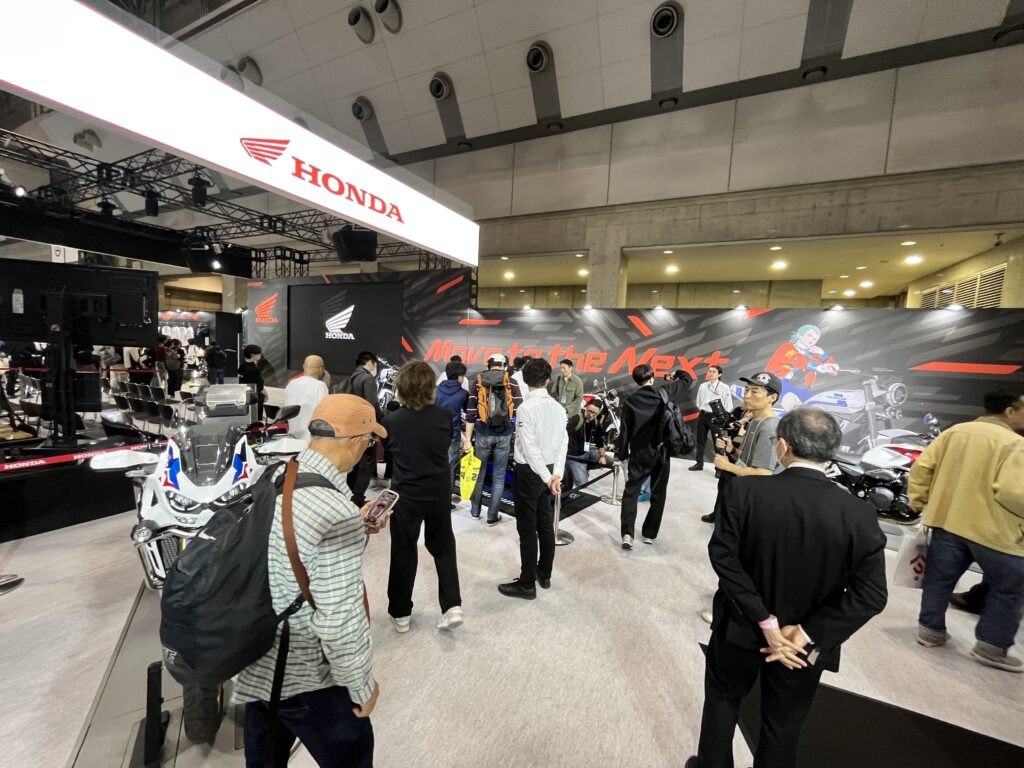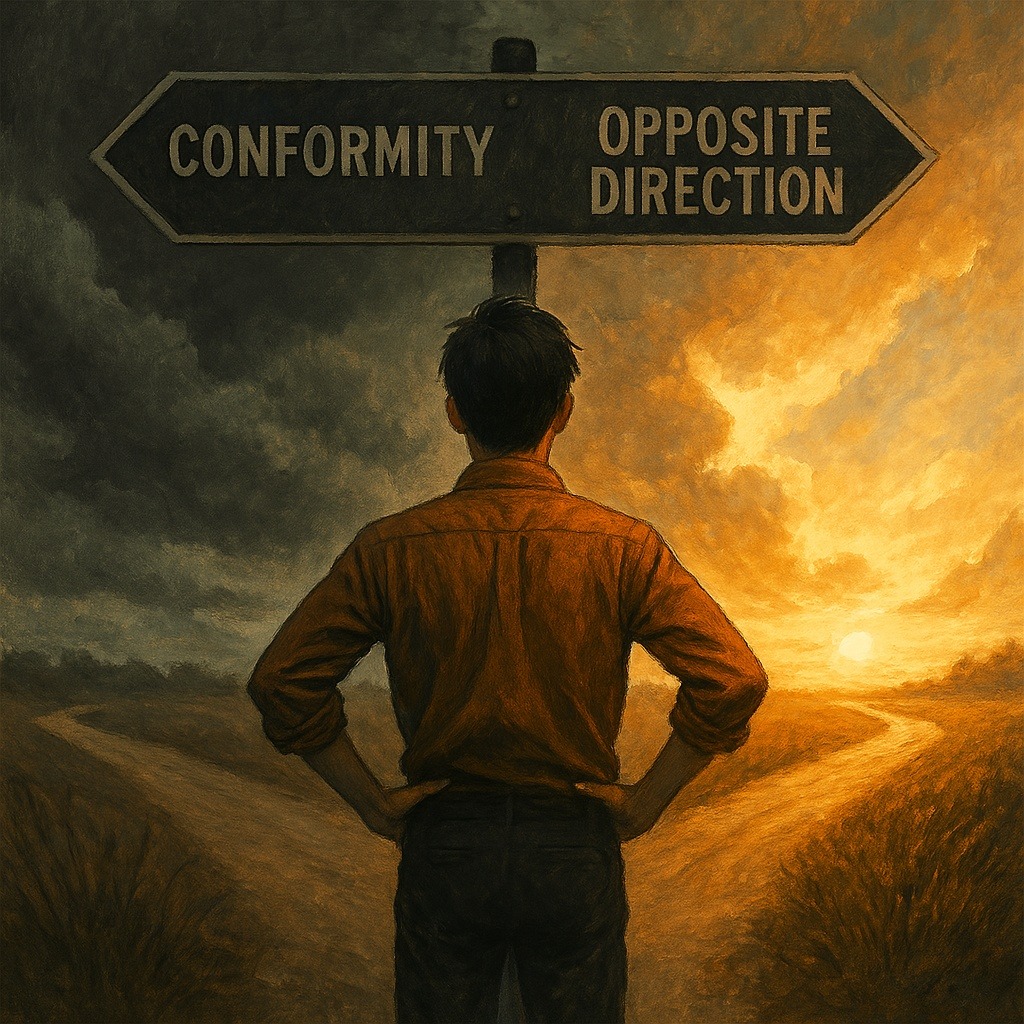AIが登場したことにより、定型的な知識や理論の価値が低下する。
これは間違いないでしょう。
ここで言っているのは、あくまでも定型的なものです。
それらが必要なのは変わらないだろうけど。
で、理論などの「すでにあるもの」は容易に入手できる時代になっている。
ただ、それらを「利用する」のは別問題です。
やらなくても分かることの価値は急激に低下するはず。
であれば今後は
知ってるかどうか
ではなく
できるかどうか
の重要性がより高まってくるでしょう。
これは断言してしまって良いと思います。
必要なのは「新しいもの」
しかも、やらなくては分からないもの
別に発明じゃ無くても良いのです。
既存の理論を利用して、新しいものを創る
それ自体をチャレンジする
そういったことが重要になるはず。
チャレンジする
と、失敗する。
それと同時に分かることがある。
それを使って再度チャレンジする
と、さっきよりはマシになる。
また、それによって分かることがある。
またそれを使ってチャレンジする
と、もっとマシになる。
これを繰り返せば、どんどん良くなる。
途中でやめてしまったらそれまで。
チャレンジは大事です。
それを継続するのも大事です。