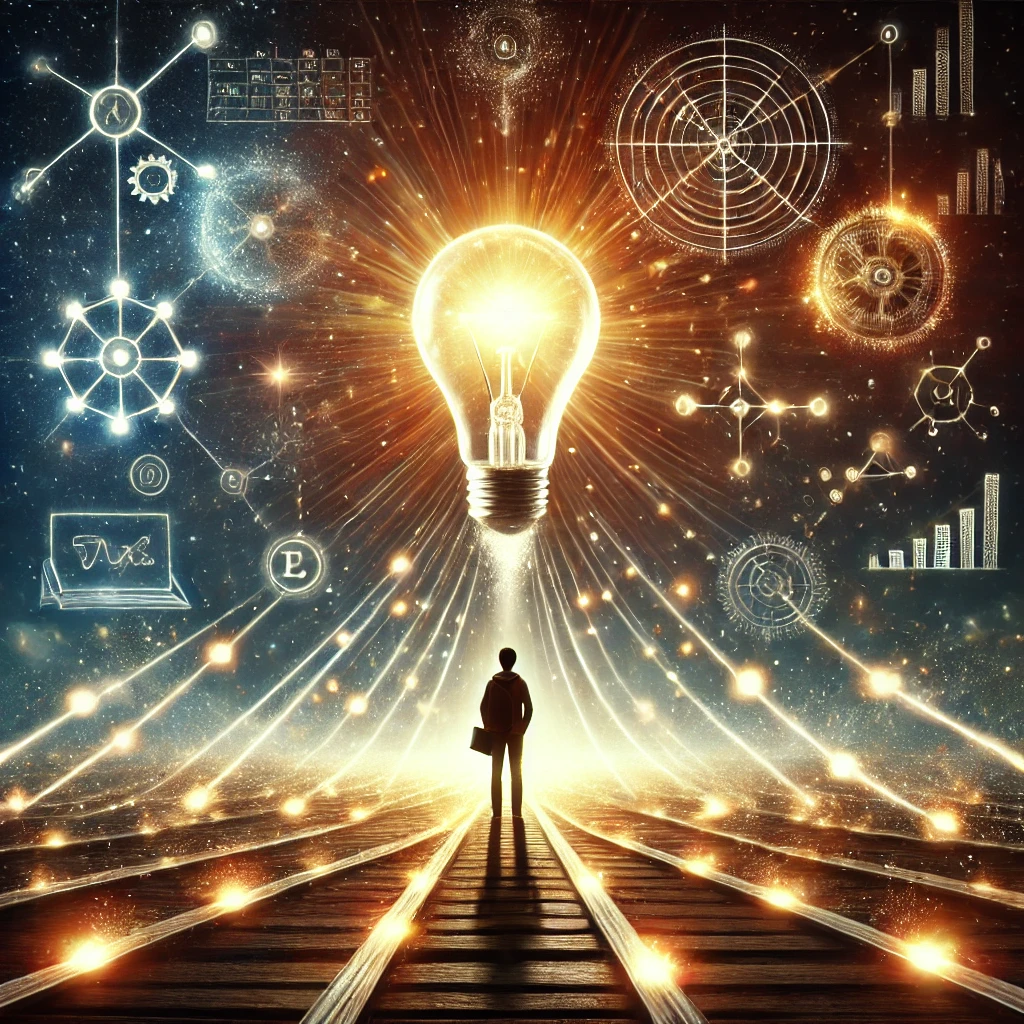日々思うのですよ。
今の日本は、面白くもないことをやらせすぎじゃないかって。
好きでもない面白くもないことをやらされて、うまく行くわけ無いじゃんか、と思います。
せいぜいマイナスが発生することを最小限にするのがオチでしょう。
面白くもないことをやって、成果を出せる人もいるでしょうけど、それはそれで凄いと思います。
けど、そうなりたいと思わないな。
就職先を選ぶ際に、将来性がある業界なのかとか、給料とか福利厚生とか、そんなのを決め手にするケース、凄く多いんじゃないかと思います。
そこで自分が何をもらえるのか、ってのが決め手なのでしょう。
そうじゃなくて、そこで自分が何を提供できるようになりたいかが重要なのですけどね。
それこそが夢の実現だし、自分が価値を提供する前にもらうことを考えてるって、何かおかしい気がするのですよ。
順番が逆では無いか?と。
好きなことをやるといっても、給料とか待遇とか将来性とかが気になる?
経験から言うと、そんなの気にしてたら自身の将来性が無くなっちゃうのではないかなと思う。
というか、今まで色々仕事をしてきて、それこそこんな給料じゃ食っていけないとか、命の危険があるとか、そんなこともあったけど、好きなことをやってきて、それらの経験で無駄になったものは無いと思っています。
全て役に立っている。
なので、全く後悔はありません。
順当で無難な道を選んでいたら、将来的に役に立つ武器を得られるチャンスは最低限になってしまっただろうと思います。
就職先の将来性なんてのも、好き勝手やってきた者からすると、そんなことを考えるのはナンセンス。
だって、将来性が見通せる仕事なんてのは、すでにうまくいっている先行者がいるわけだし、うまく行くことが分かっている仕事はいずれ必ず衰退する。
それを選ぶのは戦略的に敗北しているじゃないかと思ってしまうのです。
だったら、流行っているいないにかかわらず、好きなことなら頑張れるので、ムチャクチャやりまくれば、うまくいっちゃう可能性はある。
いや、そもそも今まで盛り上がった業界って、盛り上がる前は盛り上がってないわけで、そういうことをやりたいって他人に言ったら
「なんでそんな変なことやるの?」
「そんなの誰もやってないからやめとけ」
と言われたはず。
夢も無いのに何十年も同じ仕事を続けられるってのは凄いな、と思ってしまう。
ま、続けられなくて離職率が上がっているのでしょうけどね。
そんなものですよ。