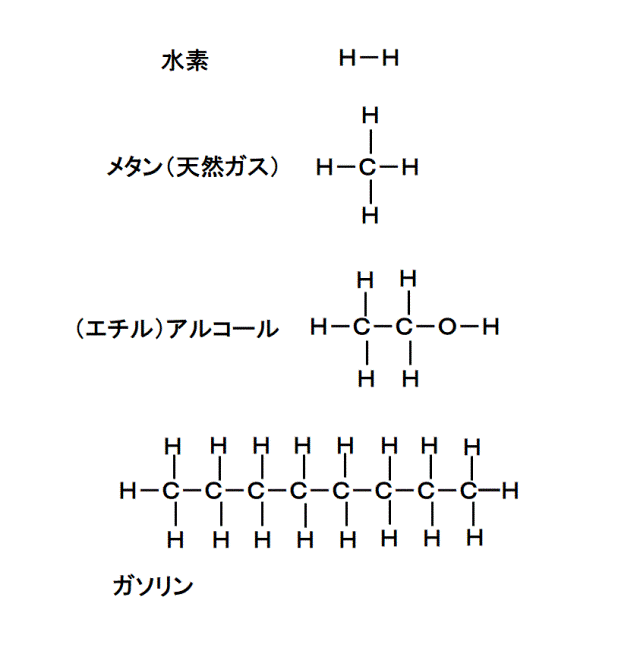専門が自動車なだけに、どうしてもクルマネタに偏る、というか、クルマに関することばかり気になってしまうのです。その辺はご容赦を。
アメリカは、先進的なところはもちろん、旧来のものを保守的に継続しているところも同居していて、その辺がとても興味深いというか、面白いと思っています。
その辺は、細かいことをいちいち上げるまでも無いと思いますが。
クルマに関しては、地域ごとに傾向が大きく異なっているのが面白いです。
それに比べれば、日本はかなり画一的で地域性はあまり感じられません。
例えば、ネバダ州ではピックアップトラックが多いです。もの凄く多い。
税金が安いからというのは聞いたことがありますが、それにしても多い。
昨年は、ピックアップトラックの巨大化に驚きましたが、今年は巨大化も一息ついた印象がありました。
対して、ハイブリッドやEVは少ないですね。アメリカとは言わず、世界的にEVの代表格であるテスラのクルマは、いるにはいますが、数は少ないです。プリウスも前年区比べれば微増といったところでしょうか。あまり見かけることはありません。
ジープタイプの四駆というか、まさにジープなのですが、これもかなり見かけました。
まぁ、ワイルドな土地柄に相応のクルマが多いということになるでしょうか。雰囲気的なものもあるでしょうが、実用性も求められているでしょうね。
当然ながら、充電ステーションも少ないです。宿の近くのWalmartに充電ステーションがあるのですが、常にガラガラです。
宿に充電設備があるところを見たことがありません。これは、我々が安い宿ばかり利用しているからかもしれませんが。
今回行ったブラックロックデザートは、最も近い地方都市であるファーンリーから100マイル(100km)ほど奥地に行ったところにあるのですが、その区間に充電設備が無いので、実質的にEVが立ち入ることは不可能でしょう。
対して、サンノゼはどうかというと、シリコンバレーという土地柄か、傾向はネバダと全く異なり、セダンタイプが多く、テスラ車もかなり見かけました。
ただし、ボディが損傷したり、バンパーが欠落していたり、リアのガラスがなかったりと、ボロボロなクルマも多いのも面白いです。
これはたぶん、所得格差なんかも原因だったりしそうな気がします。
去年に比べて、全体的にバイクが増えた気がします。
これは、ファーンリーやブラックロックデザート付近に限らず、リノの街中でも感じた事です。リノではカスタムされたハーレーをよく見かけました。
サンノゼには初めて行きましたが、結構バイクがいた気がします。
海外に行くと、クルマの種類はもちろんですが、高速道路の状況なども、その国の状態を知る指針になると思っています。
例えばフリーウェイの巡航速度ですが、アメリカは全体的に速度域が上がっている気がします。また、バーストしたタイヤの破片をあまり見なくなりました。
とまぁ、そんなことを見たりして、これは景気が良くなっているということなのかな?と思ったのですが、どうでしょうか?
でも、ガソリンの価格は、昨年比で3割くらい上がっている気がします。
全体的に経済が復調しながらも、貧富の差が拡大していうということなのかな?
そうそう!現地では、当然ながらレンタカーに乗るのですが、Apple CarPlayは便利ですね。
今まではスマホをナビに使うためにどこにマウントしようかな、なんてのが悩みのタネでしたが、今や全く問題無し。
ただ、時として接続がうまくいかなくて苦戦したりしましたが、こういうのって過渡期には仕方ないことなのでしょうね。