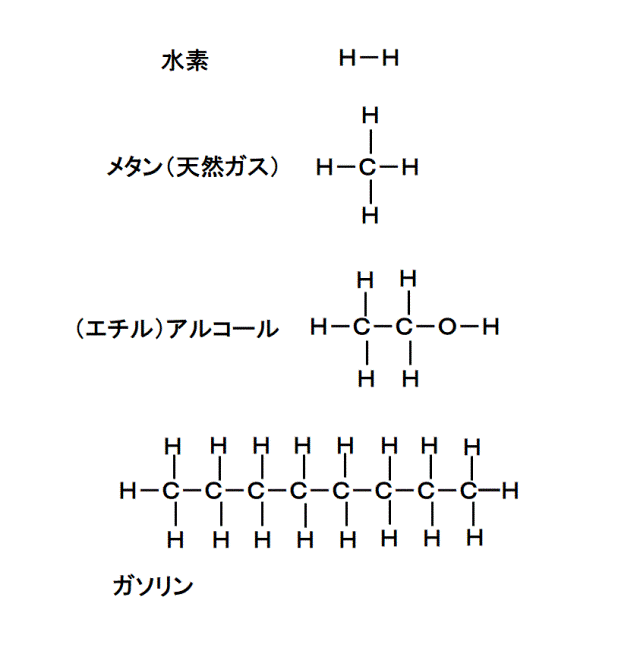「日本人は…」とか言うのはあまり好きではないのです。
だって、人によって色々違いますし。
でもやはり、傾向ってのはあるもので。
日本の教育ってあまりに受動的すぎて
目的なんて要らないのですよね。
皆が色んなことを同じようにできなければいけない
という今のやり方では
むしろそんなものがあったら邪魔なのでしょう。
そもそも教育なんてのは
何かしらの目的のための手段のはずなのに
今やそんなものは見当たりません。
手段が目的化してしまっています。
「勉強できるようになること」
「良い学校(良い会社)に入ること」
が目標になっているでしょう?
それ、本来は手段でしょう。
というか
150年前の富国強兵とか
70年前の高度経済成長と
同じやり方をしている気がするのですが
どうでしょうか?
時代が時代なら
それが必然だったのでしょう。
特定のことに対して
ある一定レベルの人材が沢山いたら
有利な時代だったわけですが
今はどうなのでしょうね。
多様化に対応しなければいけない時代に
学校に限らず社会という環境は
若者達を収束させる方向に向いたまま
のように見えます。
もちろんその環境の影響を受けた彼らは
自ら自然と収束していきます。
何のためにやってるかは分からないけど
勉強できたら何とかなるでしょう
言われたことをやればいいでしょう
みたいな感じで
皆が同じようなことを
同じようにできなければいけない
という価値観に収束していませんか?
そういうやり方じゃ「尖ったもの」は生まれません。
だってみな同じだもの。
尖りようがない。
でもこれって
安保闘争とか、校内暴力のしょうもない時代とか
そういう時代を通過して
徐々に完成形に近づいてきたってこと?
やっと皆が同じような価値観にハマって
大人しくなってきた…
ってことだとしたら、ちょっと怖いですね。
どうなのでしょうね。
その辺はよく分かりませんし
そんなことばかり考えていると
「陰謀論」みたいな
考えていても何も変わらない
不毛な世界に行ってしまいそうなので
この辺でやめておきましょう。
では、こういうのはどうでしょう?
もちろん「皆が」という前提ではないですが。
好きなことを選んで目標設定して
それを全力でやって
納得いったら卒業しろ
みたいなやり方
成績表とか卒業証書なんて
今どき何の保証にもならないのだから
そもそもお墨付きなんて無くていいじゃん
という感じ。
もちろんその過程では
アドバイスとか評価が重要になるでしょう。
学校の悪いところは
「教える」のだから
それを熟知している教員が必要で
それができる設備がすでに整っていて
全て決められたお作法に従って
「やらせる」必要があるのだ
という構造になっているところだと思います。
それじゃ新しいことはできません。
チャレンジできません。
もちろんそういう学校もあって良いのですが
他の選択肢が無いのですよね。
段位は持ってないけど
異種格闘技戦はムチャクチャ強いぜ!
みたいな人材を育てたら面白いと思います。
基本は大事?
そうですね。
だったら基本を手に入れる方法から入れ替えるってのはどう?