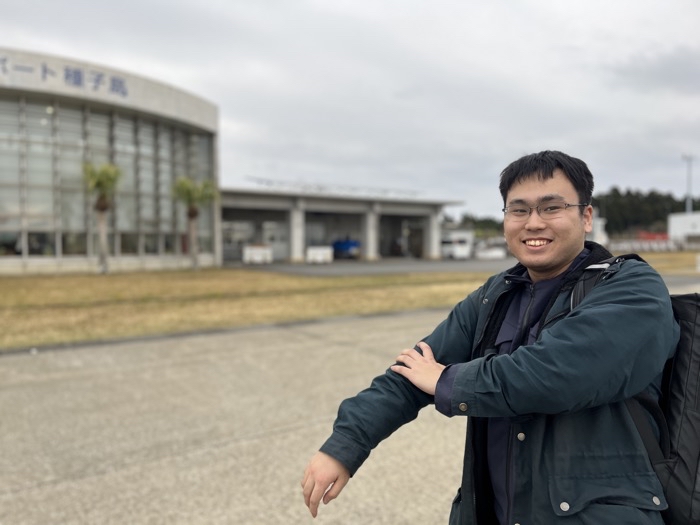昨日、種子島に着いたときからポツポツ雨が振り出しましたが、今日は朝から振りっぱなしでした。
とはいえ、チームは宿で機体整備をしているので、特に問題はありません。
今回も基本設計は従来通りの四輪駆動で、機体はもちろんカーボンファイバー製ですが、新たに作り直しました。

今回の目玉の一つ、AIを使った画像認識システム。
AIは今回が初挑戦ですが、今までのテストは概ね順調。
今回で、これまでのアピールポイントだったカーボンの強靱な体に加え、知能と目玉を手に入れたことになります。

そして、今回から無線システムもグレードアップ。
指向性の八木アンテナは、ツノダクンの手作り。
これで機体の方向を探りつつ、詳細な情報を入手しようという作戦です。
もちろん、種子島はフィールドが狭いので機体を目視できるのですが、アメリカのイベントに向けての先行研究という位置付けです。
なのでアンテナは、やや小ぶりに作ってあります。

こんな感じで作業してます。
手前にいるのはカーボン部品をはじめとするハードウェア担当のリッキー。
そしておなじみのコータローと、市場の国いるのがツノダクン。

今日で二日目なのですが、布団は綺麗に折りたたまれたまま…ということは…うん、頑張ってますね。

コータロー曰く、「明日からはテスト走行はじめます」とのこと。
期待しましょう。
天気が良かったらイベント会場となる「世界一美しいロケット発射場」JAXA種子島宇宙センターに行ってみましょう。