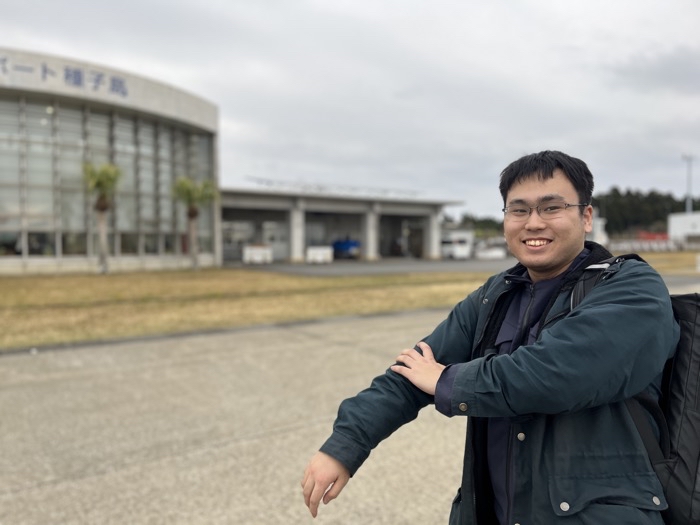それは言い過ぎ?
そうかもしれませんね。
言いたいのはこういうことです。
「勉強しなさい」
と“言われて”やるのはイヤだ。
そういう場合があります。
というか、そういう人もいます。
言われたことをやらされるのがイヤ。
特に
なぜそれが必要か分からないのに、やらなければいけない
ってのが苦手。
なので、やる気が起きない。
ということです。
でも反面、やりたいことや腹に落ちたことはできる
ということだったりもします。
しかし、この「やりたいこと」に対して
他から否定され続けてきた
とか
自信が無くて踏み出せなかった
なんて経験ばかりだと
当然ながら「やりたいこと」は、できないままになっています。
言われたことはやりたくない。
そして
やりたいことはできていない。
それはもう、単純に
「できない」状態であって
そういうのは当然自覚できるわけです。
なので、本当は興味があることがあるのに
封印されていたりすることも多いかと。
勉強できない人で
どうしたら良いか分からない人は
こういうケースも多いのではないかと思います。
で、中には「できないまま」ではイヤだ
となる人がいます。
その結果
「できない」未来に不安を感じて悩んでしまって
小さく狭い領域に入っていく人
我慢できなくなって
外に向かって踏み出す人
もしくは
そのままの人
色々でしょうね。
もちろん興味深いというか
期待が持てるのは
我慢できなくなって
外に向かって踏み出す人
です。
そういう状態になったなら
勇気を伴う行動力があって
自身の変化に対して腹が決まっていたりするので
意外と面白い成長をしたりするのです。
言われたことをやるのは苦手・できない
でも反面
言われてもいないことができる
それが人一倍できるなら
それはもう「才能」と言っても良いレベルになるかもしれません。
そういうので成功した人は
意外なほど沢山います。
開発者は、そんな人多いですよ。
「変態」と言ったら聞こえが悪いですが
変わった人多いですから。
楽しい職場です。
ところで
勉強できる人って
周囲から「勉強しろ」とか言われてないケースが多いようです。
無理強いされてないから、嫌う理由が無いんでしょうね。
まぁ大抵は、無理強いされたら嫌になりますものね。
理由も無いのに勉強できる人や
無理強いされてもできる人がいますけど
すげぇなぁ、と思います。
私は、そういうの無理ですから。
でもね
そもそも「勉強」って何なのさ?
とも思うんですよ。