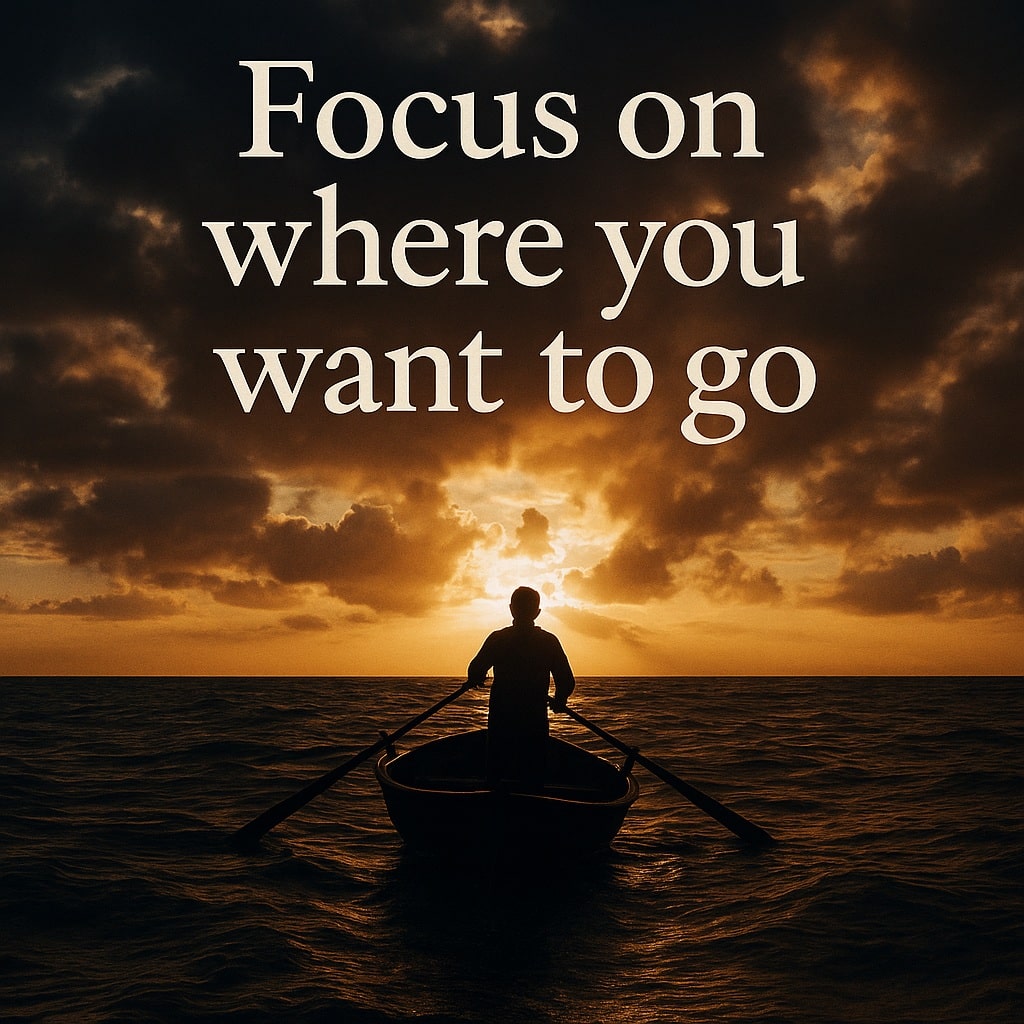
「とりあえずやってみる」
「今できることをやってみよう」
それは大変結構なことです。
挑戦の第一歩として「とりあえずやってみる」ことは大事。
でも、ビジョンが無いまま始めた行動は、どこへも辿り着かない。
ゴールが無いのだから。
方向を持たない歩みは、たとえ一所懸命であっても、漂流でしかない。
努力という名のオールを必死に漕いでも、どこかの岸に着く保証はない。
そもそも地図が無いのだから。
問題は、「どうなっちゃうか?」ではない。
「どうしたいか」が、そもそも存在していなかったりしないだろうか?
「とりあえず」で始める。
「できる範囲で」と進める。
それは結構なこと。
しかし、ゴールやビジョンが無いまま
「無理はしない」「様子を見ながら」
で進むのは大変もったいない。
そう
「とりあえずやってみる」だろうが
「今できることをやってみよう」だろうが
目指すところがあってこそ、なのですよ。
ビギナーであれば、足りないものは山ほどあるでしょう。
それは今から手に入れればいい。
勘違いや失敗もあるでしょう。
そんなのはやりながら修正すれば良い。
どうしたいのか?
それがあれば迷走はしない。
その気持ちがゴールへの道しるべであり、近づくための推進力なのですよ。


